『災害時における口腔衛生の問題』
能登半島地震は、日本における重大な自然災害の一つ。その上、先日は台風からの豪雨で、複合災害となりました。この災害がもたらした影響は深刻でした。
長期にわたる水不足、ライフラインの断絶、避難生活の不自由さの結果、特に口腔衛生が保たれなかったために、体調不良や災害関連死の原因となったケースもありました。本稿では、その原因や事実を掘り下げ、水がなくてもできる口腔ケアの重要性についてお話ししたいと思います。


能登半島地震は、日本における重大な自然災害の一つ。その上、先日は台風からの豪雨で、複合災害となりました。この災害がもたらした影響は深刻でした。
長期にわたる水不足、ライフラインの断絶、避難生活の不自由さの結果、特に口腔衛生が保たれなかったために、体調不良や災害関連死の原因となったケースもありました。本稿では、その原因や事実を掘り下げ、水がなくてもできる口腔ケアの重要性についてお話ししたいと思います。
長期にわたる被災で問題になるワードとして「誤嚥性肺炎」があります。なんとなくこのワードだけ見ると、高齢者が、間違えて食べ物を気道や肺に飲み込んでしまって起きるものと思ってしまいませんか?誤嚥性肺炎は、口腔の不衛生から細菌が増え、唾液や食べ物と一緒に誤嚥され、気管支や肺に入ることで生じる肺炎です。災害時は高齢者だけのものではなく、どの年齢でも起きるかもしれないものなのです。
誤嚥性肺炎の原因の一つとして、口腔ケアが疎かになることで起きます。
口腔ケアが不足すると、歯や歯茎にプラーク(歯垢)やバイオフィルム(歯垢が口腔内に長時間留まって膜のようになったもの)が形成され、これが細菌の温床となります。この細菌が増えると、特に免疫力が低下している人は感染のリスクが高まります。
さらに口腔内に食べ物の残りがあると、細菌の繁殖につながります。食べ物が細菌に栄養を与えることで、口腔内の環境が悪化します。
口腔ケアが不十分だと、口腔内の乾燥を招くことがあり、唾液の分泌が減ることがあります。唾液は自然な抗菌作用を保つため、その減少は細菌のコントロールを難しくします。
口腔内の衛生状態が悪化し、細菌が多く含まれる食べ物や飲み物、唾液を誤って飲み込むと、それが気管を通って肺に入ることがあります。これが、「誤嚥」につながります。肺に入った細菌が感染を引き起こし、炎症が起きることで「誤嚥性肺炎」が発生します。この病気は特に高齢者や体力が低下している人にとって危険です。
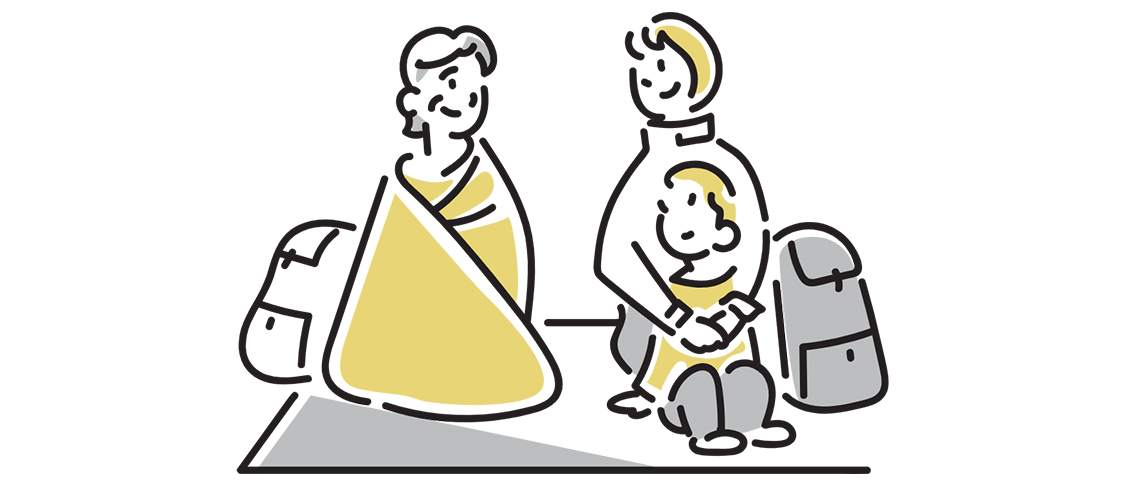
避難所では会話が減少し、ストレスや不安から人々はだんだんと口を動かさなくなる傾向があります。この結果、心のつながりも薄れ、場の雰囲気が重くなり、会話ができる状況ではなくなってしまいます。さらに、避難生活ではエンターテインメントを楽しむ余裕もなくなります。
会話が減ることは、口を動かさなくなることに繋がります。それは口のフレイル(虚弱な状態)に繋がり、嚥下行動に大きな影響を与えることになります。普段であれば考えられないことですが、唾液や食べ物が誤って気管に入ることもあり、これが誤嚥性肺炎に繋がるのです。
能登半島地震後、避難所や被災地においては水源が限られ、十分な水の確保が困難でした。そうなると、飲食用の水の使用が優先されます。その次に優先されるのは体の清潔・衛生、そして掃除です。避難時には、水がないと歯磨きができないと考える人が多くいます。そのため、多くの人が歯磨きやうがいを行えず、口腔内の細菌が増殖しやすくなりました。
特に高齢者や免疫力の低下した人々にとって深刻な問題で、口腔のトラブルが全身性の健康問題を引き起こす可能性があります。
また、避難生活におけるストレスは心身に多大な影響を及ぼします。ストレスが口腔の健康に与える影響は、食事の摂取量の減少や咀嚼力の低下、さらに神経性の口内炎などとして表れます。このような状況下では、口腔ケアの意識が低下し、さらに口腔衛生が悪化する悪循環に陥ってしまうことが多いです。
前述のとおり、避難生活では、唾液が減少し、ドライマウスに陥る可能性が高まります。ドライマウスになると唇や舌の乾燥感が出て、口の中の粘つきを感じたり、嚥下障害、むし歯のリスク増加、味覚の変化、口臭、話しにくさ、感染症のリスクが上がるなどの体への影響が出てきます。
そう考えると、唾液は本当に重要です。消化器系のサポートをする働きがたくさんあります。例えば、嚥下をしやすくすることや、消化酵素の分泌を助ける緩衝効果(pHをほぼ一定に保つ働き)などがあります。口腔内や歯の洗浄効果もあります。
唾液は99%以上が水分で構成されています。この水分によって、口腔内や歯に付着した食べかすを洗い流す役割があります。実際に、唾液の分泌量が少ないとむし歯になりやすいと言われており、この洗浄効果が重要であることがわかります。また、唾液の中には口腔を細菌から守る物質、リゾチームや免疫グロブリンAが多く含まれており、溶菌作用や免疫機能にも唾液分泌は関連します。動物がケガをした時などに傷口を舐める行動をするのは本能的にこの働きを知っていることによる自己治療行為なのかもしれませんね。
その他にも衛生効果があり、口腔内が傷つかないように、保護する働きや歯の石灰化を促進するような働きがあると言われています。
普段なら唾液が出て生活ができている。しかし災害時は水が少ない。喉を潤す機会も減る。長期の避難においては、まだまだエンタメもなく、精神的にも追い詰められて会話も表情も乏しくなってしまう。口そのものが老化してしまって、二次災害が起きてもおかしくない状況になります。だから唾液が出せる生活ってとっても大事なんです。
水がない状況でも、口腔ケアを行う方法はあります。
1. うがい薬の使用
薬局等で手に入る殺菌性のある洗口液を準備しておくことで、口腔内の清掃が可能となり、衛生状態を保つことが出来ます。
2. 湿らせたガーゼやスポンジの使用
水が使えない場合でも、湿ったガーゼやスポンジを用いることで、歯や舌の表面を清掃できます。これにより、食べカスや細菌を除去することができるのです。
3. 口腔保湿剤の活用
口腔内の健康が損なわれないよう、口腔用の保湿剤を使用して潤いを保つことが重要です。特に高齢者や持病のある方には欠かせません。
ここで、特に手軽にできる方法をご紹介しましょう。ペットボトルのキャップに水を入れ、口をつけないようにして口腔の中に水を落とします。口を閉じて10秒間我慢すると、唾液がじわっと出てきて、そのまま飲めば口が潤います。そのままうがいも可能です。つまりキャップ1杯の水だけで口を濯ぐこともこれなら可能です。災害時は日常の行動の半分しかできません。だからこそ、何も起きてない今のうちにこの体験をしておいてください。
また、避難所で試みた唾液の分泌を活性化させる意外な方法をご紹介します。避難所で試したのは、昭和歌謡を小さい音量で流すことでした。この方法は、実際に能登半島の避難所で試して非常に効果があり、皆さんが喜んで実践したものです。
最近の昭和レトロブームにより、若い人でも昭和歌謡を知っている人が増えています。年齢に関係なく知ってる歌があるので、避難所で流れているとなんとなく口ずさむ方が多いのです。さらに、老若男女問わず会話のきっかけになります。殺風景でみんなあまり会話をしなかった避難所の雰囲気が明るく変わりました。
歌を歌うことで口を動かし表情が変わり、そして唾液が出るようになりました。
昭和歌謡が流れていることに慣れてきたら、平成ポップスとか令和ソングスとか、いろいろな時代の曲を流していただくようにしました。さらに会話が増えます。たまにスタッフが突然歌い出すとか、踊り出すとか、そういうサプライズもしてもらうようにしました。
そのような行動で避難所そのものの空気も変わり、被災者同士のコミュニケーションも増えてきました。風通しが良くなってきて、揉め事も減ったんです。そして、なんと食事の摂取量が上がり、咀嚼時間も上がり、皆さんの気力がみなぎってきていることが手に取るようにわかりました。
一見すると「たかが昭和歌謡」かもしれませんが、実際には大きな力を持っています。簡単で、誰でも、いつでも、気軽にできる。その上めちゃくちゃ楽しい。そうでなくっちゃ続けることなんてできません。いくらボランティアや団体がやってきて、歯ブラシを渡して、これで歯を磨いてくださいと言われても、なかなか歯を磨くとはいかないものなんです。
私は常に、避難所での生活はもっと豊かなものに変えるべきだと強く思っています。何かおもろい、何かわからんけどやってみたくなる。そういうものって日常生活にはたくさんありませんか?避難生活だからってそういうものが全くないって…生活なんだからおかしいと思います。もっともっと日常生活に近づける避難生活を想定してみてください。
今日のお話は、水がない状況における口腔衛生の重要性についてでした。普段の生活でも、歯磨きやうがい、水分補給を心がけ、口腔内の衛生を維持してください。
